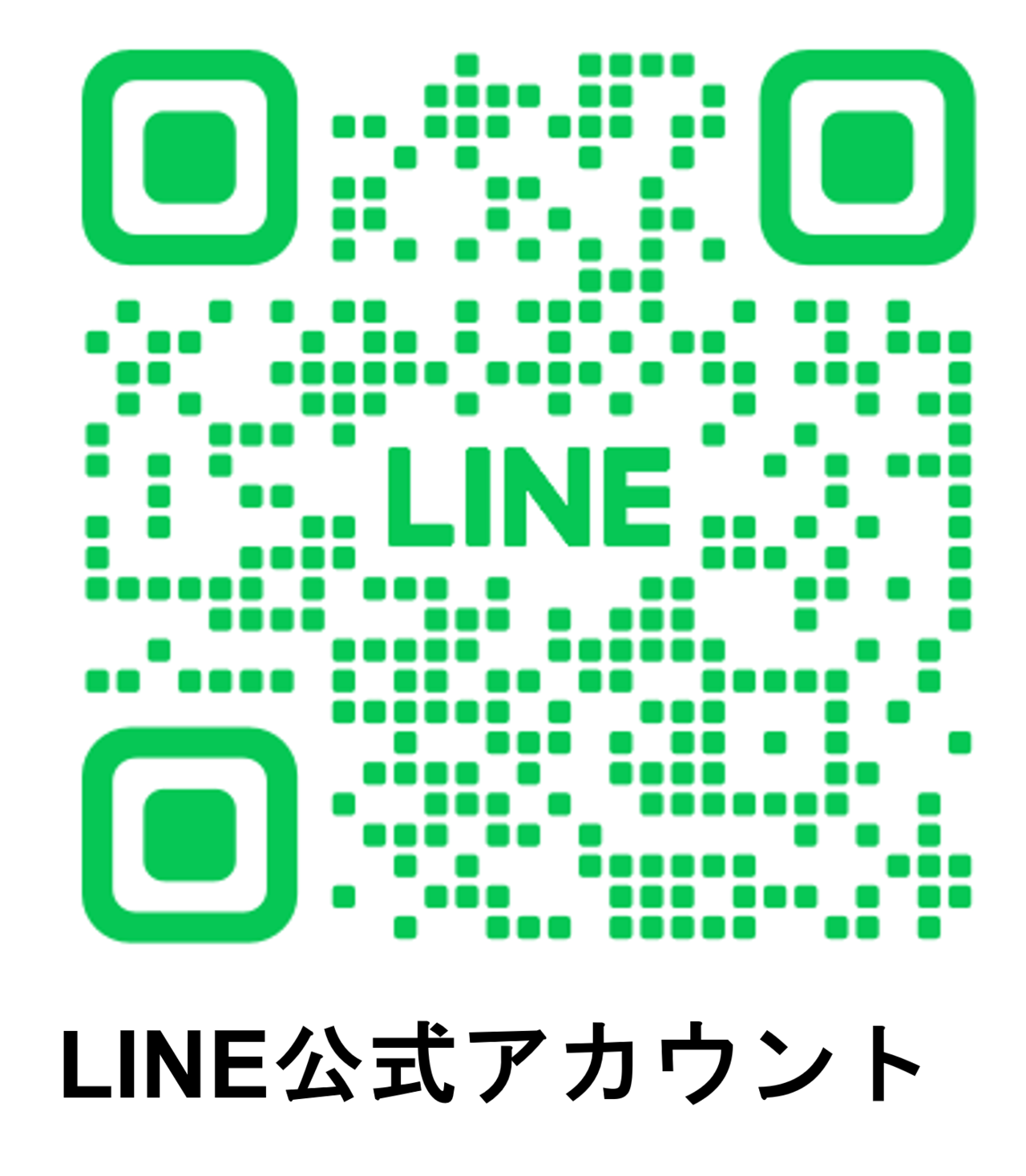- トップ
ページ - リハビリ
サービス - 高齢者
在宅 リハビリ - 高齢者
施設 リハビリ - シニア トレーニング
- よくある
ご質問 - お問合せ
- ごあい
さつ - お役立ち
情報
老後の不安を解消する方法
~2000万円がなくてもゆとりをもって老後を送るには~
これは先に結論を申しておきます
「老後をどう過ごすのか」これは人それぞれ価値観が異なります。ですので「2000万円もいらない」と考えておられる方もいらっしゃいます。こういう方は、そもそもお金で解決しようとはされていません。お金に頼らず、「自分でできることは自分でする」という考えですね。
65歳より75歳、そして80歳、85歳・・・。当然、体力は落ちていきます。だから特にシニアの方は今のうちにしっかりと体力づくりをしておくことが、結果として何百万円、何千万円とお金を節約する事に繋がるでしょう。
もちろん、80歳、85歳になっても体力はつけられますし、われわれもリハビリを行います。ですが、やはりリスクを伴いますし、ご本人の気力も不可欠です。こればっかりは早いうちに始めるに越したことはありません。

老後に2000万円は本当に必要?
みなさん、「老後2000万円問題」をご存じでしょうか?
定年後、老後に必要な資金が平均して2000万円程度必要であるとの試算結果が話題になりました。
これは2019年金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書にあったものです。このワーキング・グループは平成30年9月より計12回にわたり、「高齢社会における金融サービスのあり方」など「国民の安定的な資産形成」を中心に検討・審議を行っておりました。
「そんなに貯金はないよ!」と不安に思われた方も少なくないでしょう。
これは老後の生活において、公的年金だけでは約5.5万円が毎月不足となり、65歳から30年間の計算で、
5.5万円 ✕ 12か月 の 30年間=1,980万円
がさらに必要だ、という算出方法のようです。
20年間なら・・・ 1,320万円、
15年間なら・・・ 990万円、
ということになります。
平均寿命が延長されてきているとはいえ、定年後30年間も何もしないという設定もやや現実的ではないかも知れませんが、15年あたりだと十分考えられる範囲ではないのでしょうか。
老後の不安はやっぱり健康
平成28年厚生労働白書において、老後に不安なことに関するアンケート調査結果が記されています。
グラフをご覧ください。
1位は健康上の問題、2位は経済上の問題となっています。
やっぱり健康がイチバン、ですね。
体が不調だと、それだけで通院などの治療費に支出がかさみます。体力や食事面などで制限があると、外出や旅行、趣味などを楽しむこともできません。
これでは2000万円以上の貯蓄があったとしても、何にもなりませんよね。
大前提として「老後も楽しみたい!」と思っていて、
お金はそのために使いたい、
治療・介護費用にはなるべくお金を使いたくない、はずです。
2016年「高齢社会に関する意識調査」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング:厚生労働省政策統括官付政策評価官付室委託)
持続可能な唯一の方法
近年、「自分の介護で家族には迷惑をかけたくない」と考える方が増えています。
潤沢な経済力でもって、さまざまな介護サービスなどを使い、家族・身内に迷惑をかけない方法もあるでしょう。
ですがこれだと長い長いトンネルを通るようで、いつまで続けられるか分かりません。それに、その経済力も確かなものとは限りません。
「持続可能な唯一の方法」は、今のうちから体を動かす習慣をつけて、健康になることです。
もっともコストがかからず、効果は持続的です。さらに体調が良くなり体力もつくと外出や趣味、旅行やスポーツなど充実した時間を過ごすことができます。そしてまた体力がつく・・・、という好循環が生まれます。
お金は最低限あればいいはずです。それよりも心身ともに健康でイキイキとした毎日を過ごすことが何にも代えがたいもの、なのです。
あなたがイキイキと生活していて、通院はかかりつけ医へ月イチ行くだけの85歳だとすれば、
どうでしょう。
「まだまだ!」といった気持ちで、不安どころか自信が持てますよね。
ただし、注意が必要
今、スポーツクラブやフィットネスクラブに通うアクティブなシニアの方々が増えています。
そう、皆さん健康意識が高く、
「いつまでも健康でいたい」
「若々しくいたい」
との思いを持っています。
ですが、ここでひとつ注意が必要です。
60歳~70歳のシニア世代では、やはり年齢とともにさまざまな病気やケガを起こしやすい状態にあります。
体力をつけて健康になるどころか、膝を痛めてしまって歩く事すらツライ・・・。
なんてケースは少なくありません。また、ジョギング中に胸が苦しくなって怖い・・・、という声も聞かれます。
最近はYouTubeなどの動画で、簡単にトレーニング法を調べることができます。
でも、それがあなたの身体にとって最適とは限りません。
「自己流は事故流」といいます。
また、もともと高血圧・心不全・糖尿病があるけれど、なんとか自分なりに頑張りたい、という方は、どうすればいいのでしょう。
それは、「自分の体に合った運動をすればいい」のです。
まずは、かかりつけ医へ運動について相談をしましょう。そして、理学療法士などの専門家に相談しながら、適切な運動方法・運動量を選ぶことが重要です。